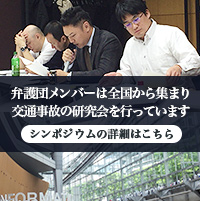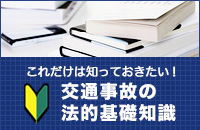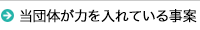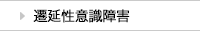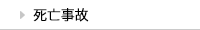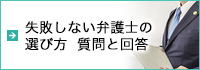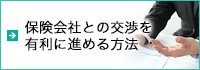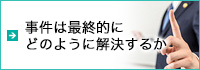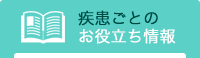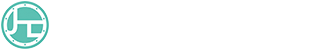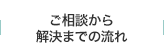数日生存後に死亡事故となった場合に請求出来る保険金は?

死亡事故と言うと、「即死で交通事故現場で死亡が確認されることが多いのではないか?」と思うかもしれません。
しかし、実際には病院に搬送されてから死亡が確認されたり、治療をしている途中で亡くなってしまうことが多いです。
警視庁が発表している交通事故による死亡者数は、「交通事故から24時間以内に亡くなった人数」ですので、24時間を超えてから死亡する被害者も多くいます。
警視庁発表の統計によると、2016年の交通事故の30日以内での死亡者数は4,859人で、そのうち24時間以内に亡くなった方は4,117人ですので、24時間を超えて30日以内に亡くなった方は742人に上ります。
警視庁の調査でも、30日以上生存後に死亡した事例の統計が取れていませんので正確な数字は分かりませんが、5~10%の200~400人程度はいるのではないかと思われます。
そのため、死亡事故の保険金と言っても、即死の場合と治療をして数日間生存したのちに死亡したのでは、補償される内容が変わってきます。
死亡に関する補償と生存中の補償の両方が受けられる
即死の死亡事故の場合には、死亡慰謝料と逸失利益が支払われます。
仮に交通事故から30日後に死亡した場合は、生存をしていた30日間に関しては傷害の人身事故と同じ補償が受けられます。
具体的には、入院治療費・入院慰謝料・サラリーマンなどで収入があった場合には休業補償・家族の介護が必要であった場合には介護費・入院雑費などが、損害補償として支払われます。
死亡したのちは死亡慰謝料と逸失利益が支払われますので、即死の場合の死亡事故よりも数百万円の保険金が多く支払われることになります。
しかし、保険会社の中には、入院治療費は病院に支払わなければいけないために実費を支払いますが、入院慰謝料や休業補償などは、死亡慰謝料と逸失利益を支払うことにより、うやむやにしてしまうことがあります。
数千万円払われる死亡慰謝料に比べれば、微々たる金額だと思うかもしれませんが、正当に受け取ることができる保険金を受け取らない理由はありませんし、何より残された家族の生活を考えれば受け取って当然とも言えます。
ですが、「弁護士に相談して初めて、そういった補償も受け取れることを知った」と言われる死亡事故の被害者家族の方も多くいらっしゃいます。
そのため、保険会社からの示談交渉があった場合には、示談してしまう前に弁護士に相談をしてみた方が良いでしょう。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
介護人が死亡事故に遭うと、被介護人の処遇が問題となるが、保険会社からの介護料の補填はないので、通常の保険金で被介護人の処遇を考える必要がある。
自動車保険と一口に言っても、補償対象が特約により細かく分類され、補償の条件が細かく指定されているので、死亡事故のような大きな事故であっても保険金が支払われないこともある。
死亡事故で自賠責保険に請求する場合には、被害者請求の方が早く遺族に保険金が支払われる可能性が高いが、書類が必要であったり加害者と過失割合の合意が必要なので、弁護士に依頼をする方が良い。
死亡事故で自動車保険と生命保険の両方の支給要件を満たす場合、両方から保険金を受け取ることができる。
家族が死亡事故に遭った場合には示談交渉を行うが、損害賠償請求権の時効は事故日から5年である。しかし、提訴や催告、承認などで時効の更新(中断)を行う事が出来る。