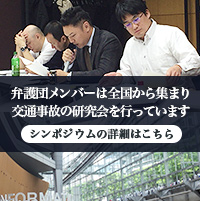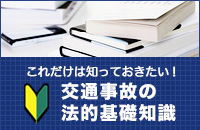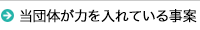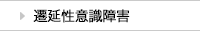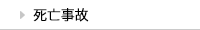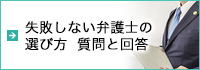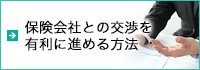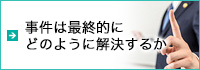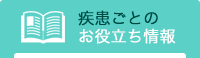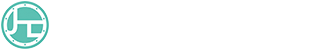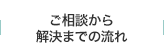飲酒運転による死亡事故で、加害者が背負うべき重罰

2007年に飲酒運転の罰則の強化がされたのにもかかわらず、飲酒運転は完全に無くなりません。
交通死亡事故のニュースのほとんどが、運転手が飲酒運転であります。
もちろん飲酒運転の死亡事故である方が、話題性があるからニュースになると言う事もありますが、実際の統計でも飲酒運転の危険性は立証されています。
警視庁の発表のデータを見ると、飲酒をしていない人の運転の死亡事故率は0.6%に対し、飲酒運転の場合の死亡事故率は5.69%と10倍近い発生率です。
しかも、飲酒運転のうち正常な運転が出来なくなる酒酔い運転では、死亡事故率は約35倍にもなるため、いかに飲酒運転が危険であるかわかります。
飲酒運転で死亡事故を起こした場合には、被害者や被害者家族に対して重い罪を背負うだけでなく、自分自身にも大きな罰が与えられます。
罰金や懲役刑などの刑事責任に加え、免許取り消しなどの行政責任はマスコミなどで報道されているので理解している方もいるでしょうが、あまり焦点が当たらない民事や経済的な点から説明をしていきます。
飲酒運転の死亡事故では、抱えきれない負債を負う可能性が
自動車保険に加入している場合には、加害者が飲酒運転であっても死亡事故の被害者に対して損害補償金が支払われます。
これは保険が被害者救済を目的としているためで、被害者が不利益を被らないための保険の基本理念と言えます。
しかし、加害者側に関しては飲酒と言う重大な過失が有るため、保険金は支払われません。
つまり、加害者自身が事故で大けがを負っても治療費は支払われませんし、会社を休んだことによる休業補償も支払われません。
しかも、飲酒運転であると健康保険も使えませんので、治療費は全額負担となるため、1カ月の入院費が100万円近くになるになる事も珍しくありません。
自動車が大破したとしても車両保険も使えませんし、もし加害者自身も事故で死亡しても保険金は支払われません。
そのため、「自動車保険のおかげで何とか被害者への損害賠償は出来たけれども、自分の方は会社をクビになって収入がない上に、治療費も多額にかかり後遺症も残った。しかも死亡事故だから前科者で再就職も出来ない」と言う窮地に陥るのです。
飲酒運転による事故が、被害者だけでなく加害者も苦しめることがよくわかると思います。
「加害者は自業自得」だけでは済まず、場合によっては家族をも巻き込んでしまうため、「飲んだら乗るな。乗るなら飲むな。」と言う気持ちを忘れないようにしましょう。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
家族が死亡事故に遭った場合には示談交渉を行うが、損害賠償請求権の時効は事故日から5年である。しかし、提訴や催告、承認などで時効の更新(中断)を行う事が出来る。
保険会社が提示する損害賠償金額は、自賠責基準とほとんど差がない。死亡事故の場合の自賠責基準と弁護士基準について見てみると基準額の決め方が異なり、数百~一千万円以上の差が出る可能性がある。
死亡事故の被害者が未成年であった場合は、18歳以上の給与所得者などとは異なる計算方式で逸失利益が計算される。
死亡事故における自賠責保険の支払いは、過失割合による独自の減額割合でなされるが、自分の過失割合が低くても相手への弁済が高額となる事もあるので注意が必要である。
交通死亡事故でひき逃げや飲酒運転、証拠隠滅など加害者に悪質な事由がある場合、慰謝料が増額された判例がある。賠償金額が大きく違ってくる可能性があり、交通死亡事故に強い弁護士へ相談すべきである。