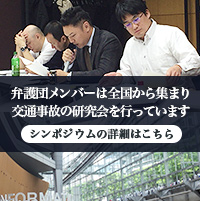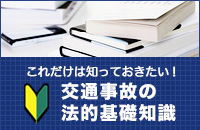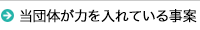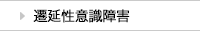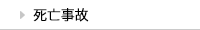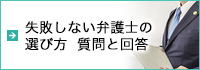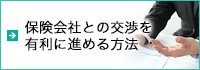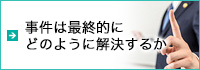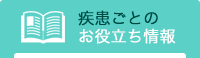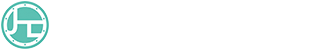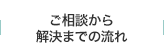交通事故による脊髄損傷の後遺障害等級と具体的な症状とは

交通事故で負った脊髄損傷は、その症状の度合いにより後遺障害等級が分かれます。
後遺障害等級は、その後の慰謝料等を請求する際に、額面に大きく影響する要素であるため、正しい主張を行うべきです。
脊髄損傷の場合、大きく分けると7つの等級に区別されます。
第1級1号、第2級1号、第3級3号、第5級2号、第7級4号、第9級10号、第12級12号の7つが、それにあたります。
症状が重篤なものであるほど、第1級に近づき、比較的軽い症状であるほど第12級に近づいていきます。
等級に応じて、症状例はある程度定められており、例えば第1級1号の場合は、神経系統の機能、または精神に著しい障害を残しており、常に介護が要するものとされます。
対して第12級12号の場合、局部に頑固な神経症状を残すものがそれに当たります。
このように、症状が重く、他者による介護が求められるような症状になるほど、後遺障害等級はより上位のものに値するのです。
脊髄損傷の具体的な後遺障害等級の区別
脊髄損傷の後遺障害等級、第1級1号のように神経系統の機能、または精神に著しい障害を残しており、常に介護が要するものであっても、具体的な症状が想像しづらいと思います。
第1級の場合の例として、高度の四肢麻痺や対麻痺が認められたり、四肢麻痺や対麻痺によって食事や入浴、用便や更衣に介護を要したりする状態を示します。
要するに、交通事故による脊髄損傷が原因で、自立して生活するのが難しい、常にあるいは随時介護が求められる状態になるほど、等級は上位になるのです。
また、四肢のどこに麻痺を生じているかも重要な点ではあるものの、麻痺の程度についても等級の申請において重要な要素です。
症状の程度は大きく3段階の、高度、中程度、軽度に分けられます。
例えば高度の場合、障害が生じている四肢において、運動性や支持性が失われ、基本的な動作ができない状態です。
ここで言う基本動作とは、上肢の場合は物を持ち移動させるような行動、そして下肢の場合は歩行などの動作を示します。
対して軽度の場合、障害が生じている四肢の運動性や支持性が多少なりとも失われており、基本動作の速度であったり巧緻性たるものが損なわれていたりする状態です。
例えば障害の残る上肢では文字を書きづらい、歩くのが遅くなったり杖等の装具が必要であったりする状態を言います。
脊髄損傷の後遺障害等級は、これらのような具体的な症状、程度を判断材料の一つとして、検討されます。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
脊髄損傷と一口にいっても、必ず上位の後遺障害等級に当てはまるとは限らない。当該症状に応じ、認定される等級は異なり、等級が高いほど慰謝料の額にも関わる。
脊髄損傷の症状は四肢の麻痺が代表的なものであるが、一見して脊髄損傷によるものとは分からない症状もあるため注意が必要である。
交通事故に遭って脊髄損傷を負った場合、排尿障害が起こることがある。症状や被害者の年齢によっては、後遺障害の認定で争われることがある。
交通事故で受傷した脊髄損傷は、後遺障害等級の認定を受けられれば高額の慰謝料を見込める。今後の人生を大きく変える怪我であるため、納得いく金額を受け取るために、弁護士に相談するべきである。
脊髄損傷のなかでも頚髄が損傷すると、自律神経障害がみられることがある。症状として体温調節機能の低下や血管運動神経の障害、異常疼痛や異所性骨化などがみられる。