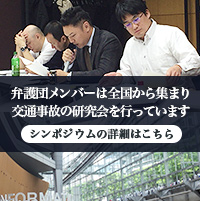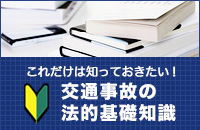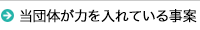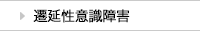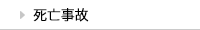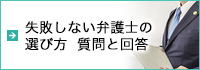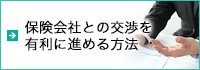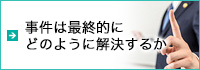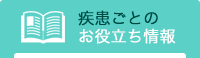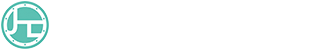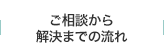交通事故で脊髄損傷となった場合の逸失利益について

交通事故で脊髄損傷を負った場合、高い割合で麻痺や感覚不全などの障害が現れます。
現在の医療技術では脊髄損傷は完治不可能であるため、現れた障害は『後遺障害』とされます。
交通事故で脊髄損傷を負い後遺障害が現れた場合には、受傷者は『後遺障害慰謝料』を加害者に請求します。
後遺障害が残った場合には、後遺障害慰謝料とは別に『逸失利益』を請求する場合もあります。
交通事故で後遺障害を負った場合、交通事故以前の仕事を続けることが出来なくなったり、処理できる仕事量が減ったりして減収が考えられます。
この、収入の減少分が逸失利益と呼ばれます。
逸失利益の計算方法は、給与所得者ならば『年収×後遺障害等級による労働能力喪失率×ライプニッツ係数』になります。
労働能力喪失率とは後遺障害で働く能力が減った(収入が減った)ということを表しており、後遺障害等級第1級ならば100%、第14級ならば5%と、等級ごとに決まっています。
ライプニッツ係数は複利計算で用いられる係数です。
例えば、交通事故で脊髄損傷を負い後遺障害等級第1級となった場合、労働能力喪失率は100%なので、事故後の収入は0円ということになります。
被害者が年収500万円であと20年間働けたとしたら、1億円の収入減です。
示談金は一括して支払われることがほとんどなので、1億円を支払われればよいと思うでしょう。
しかし、1億円を受け取って年利3%の定期預金に預けた場合、毎年300万円の金利による収入が得られるため、支払う側としては過剰な支払いとなります。
ですので、年利3%の定期預金に預けつつ、毎年500万円を使っていって、20年経った時点でちょうど使い切れるように計算された逸失利益を支払われるのが一般的です。
脊髄損傷でも必ず逸失利益が発生するわけではない
脊髄損傷で後遺障害が残った場合、高い確率で逸失利益を請求できるのですが、被害者が想像していた金額に満たなかったり、逸失利益が得られないこともあります。
逸失利益は、『脊髄損傷の後遺症がなければ失わなかった利益』のことですので、脊髄損傷の後遺症があっても、収入が減少しなければ逸失利益は発生しません。
家賃収入で生活しているなど、いわゆる不労所得者の場合には、後遺症が残っても収入が発生するため逸失利益は発生しません。
会社員などの給与所得者でも、後遺症による給料の減額がなければ、逸失利益は発生しません。
また、逸失利益にかかる労働能力喪失率は、脊髄損傷患者の就業状況にそぐわないケースがあり、裁判でも争われることがあります。
例えば、脊髄損傷で右足が完全麻痺で後遺障害等級第5級に認定された場合、労働能力喪失率は79%です。
会社員でデスクワーク中心ならば、事故前と変わらず仕事が出来る可能性がありますが、宅配の運転手ならば運転が出来ないだけでなく、荷物の持ち運びや搭載などが出来ず、退社せざるを得ないかもしれず、79%の給与補償では納得がいかないと思われるケースもあります。
逸失利益は後遺障害等級から計算されるのがが基本となりますが、判例では労働能力喪失率について被害者の状況によっては増減することもあるため、逸失利益に疑問があれば弁護士に相談しても良いでしょう。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
脊髄損傷患者の多くは足に障害が出るため、歩行や移動に関して問題を抱えることになる。将来的な歩行・移動補助道具の購入費用も交通事故の相手方に請求できる。
脳の底部から背骨へと延びている太さ約1cmの神経である脊髄を交通事故などの外部からの衝撃で傷付け、さまざまな病状を発症するのが脊髄損傷である。
交通事故により脊髄損傷を負い、歩行困難となった場合には、移動に必要な杖や車いすの購入費用のほかに、福祉車両や民間救急車などの移動手段についても請求できることがある。
脊髄損傷は損傷の程度により、足先の痺れや、下半身麻痺であったりと症状にばらつきがある。交通事故による怪我が原因で生活が困難になった場合、リフォーム費用を加害者側に請求できる可能性がある。
交通事故による脊髄損傷で後遺症があった場合でも、逸失利益が発生しないケースでは相手側に請求することができない。